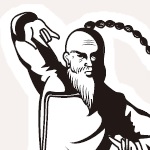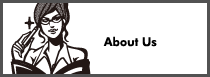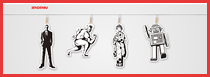以前もブログで「20:80の法則」を紹介したが、理解していない人が多いので再度紹介しよう。「20:80の法則」は19世紀のイタリアの経済学者であるヴィルフレド・パレートによって提唱された法則で別名「パレートの法則」とも呼ばれる。この法則は物事の結果のうち80%は20%の要素によってもたらされると言うものだ。
パレートは高額納税者の税金を調査すると20%の高額納税者が全体の税金の80%を納め、残り80%の納税者が全体の税金の20%を納めていることに気付き、20%の富裕層が社会全体の富の80%を所有していることが分かった。
このように当初は所得配分に対して用いられる法則だったが、その後、経営やマーケティングなどにも応用できるとされ、ビジネスの領域でも広く使われるようになった。マーケティング分野では「売上の80%は顧客の20%が生み出す」、「売上の80%は20%の商品が生み出している」、「企業の売上の80%は20%の社員で生み出している」とよく言われる。
先日、あるお得意先の販促物の印刷を進めていると、色校正を虫眼鏡で覗かなければわからないほどの細かな画像の傷や汚れをいくつも指摘してくる。しかもその作業を4人で行っていると言うので僕は驚いた。僕は老眼なのでルーペで確認したが、決して気になる傷や汚れではなかった。果たしてこの仕事の進め方は正しいのだろうか。
100%の仕上がりを追求することは大切で素晴らしいことだと思うが、20%の時間と労力で80%の仕上がりを実現できる。100%の仕上がりにするためには残り80%の時間と労力が必要になるので、その時間と労力を多少他の仕事に振り向けた方が効率良く仕事ができるのではないだろうか。仕上がった販促物を手にした消費者がルーペで細部まで確認することはまず無いだろう。
このような文化がその企業の中で広がると全ての部署で同じ考え方が根付き、「20:80の法則」を理解し効率良く仕事をしている社員は仕事の取り組み方ややり方が間違っていると非難される。
「20%の社員が80%の売上を生み出し、20%社員が80%の利益を生む」
この「20:80の法則」の面白いところは80%の売上を生む20%の優秀な社員だけを集めて新プロジェクトや新会社を立ち上げると、その優秀な社員の中で新たに「20:80の法則」が働き20%の優秀な社員とそうでない80%の社員に分かれるという。
ひょっとすると仕事のできない80%の社員は企業にとって必要悪なのかもしれない…。
written by マックス
今週、数年ぶりに大型台風が九州を襲った。この台風は気圧が925ヘクトパスカルと過去に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風と勢力がほぼ同じだったので、僕は台風にしっかり備えることにした。懐中電灯、ランタン、カセットコンロを準備し、窓ガラスが割れ飛散しないように窓を養生した。
台風が来る前日の朝、僕は養生テープを購入するためホームセンターへ出掛けた。ホームセンターの駐車場は既に車が一杯だったが何とか車を止め店に入ると、レジには懐中電灯や養生テープなどを求める客が列を作っていた。急いで養生テープの売り場に向かうと、既に養生テープは品切れだったので別のホームセンターに急いだ。しかし別のホームセンターでも養生テープは既に売り切れていたので、僕は仕方なく自宅戻った。そして自宅にあるもので窓を補強できないかと考えていると、台所にあったサランラップが目に入り、サランラップを窓前面に張り付け、その上にガムテープで補強することを思いついた。
全ての窓ガラスを補強し、ベランダにある植木鉢などを部屋に入れ、最後に愛車を守るため頑丈な建物の有料駐車場に愛車を移動させた。皆、考えることは同じようで頑丈な建物にある駐車場はマイカーを避難させるためどこも一杯だった。僕は運良く駐車場を確保することができ、台風対策で忙しく慌しかった1日は終わった。
深夜、「ゴォー」と響くような強い風の音で目が覚め、時計を見ると午前3時半。カーテン越しに暴風で今にも割れそうな窓から恐る恐る外を見ると、街路樹が折れそうなほど大きく揺れており、部屋から見える川の水面は強風に煽られ雨と一緒に水しぶきが舞っている。リビングでテレビを付けると台風は福岡に最接近していた。もう少し寝ようと床に入ったが大きな風の音で眠ることはできず、結局、朝まで起きていた。テレビには倒壊した家屋や鉄柱の折れた電灯、それに風に飛ばされる看板など台風被害の映像が幾度となく流れていた。朝7時を過ぎると風は徐々に収まり9時には随分と落ち着いて来た。その日は全ての学校は休校で交通機関も計画運休しており多くの企業も休みだったので、サランラップを貼った窓からは車も人影も全く見えなかった。
子供の頃は親の台風の備えを手伝うこともなく、停電すると懐中電灯や蝋燭の明かりで一晩過ごすことが日常とは異なりワクワクしていたが、今は自ら台風の備えをするので台風が鬱陶しく思う。台風が去り、窓ガラスに貼ったサランラップとガムテープを剥がしていると、母がこう言った。
「そのままにしとけばいいのに。また直ぐに台風は来るよ!」
台風の備えも手伝わず、慌しく動く僕を他人事のようにのんびり見ていたお袋は、ひょっとすると台風が来ることを楽しみにしているのかもしれない…。
written by ダニエル
今週も暑い、暑い、暑い~!!先週は福岡で37.5℃と過去3番目の暑さを記録し、まるでインドかアフリカのような猛暑が続いている。こう暑いと日本の食文化は変化しインドのようにスパイスの利いたカレーを毎日食べることになるかもしれない。僕はスポーツをしないが通勤するだけで真っ黒に日に焼けしてしまい日本人には見えない。
ところで企業が上場すると、売上はもちろん利益を徹底的に追求する利益至上主義になるため、有能な人材を募り社員教育や社員を監視するために多くの取締役も採用することになる。新たに採用された取締役は当然、自らの昇給昇格のために奮闘するのだが、中には職権乱用が甚だしい人や部下の手柄を自らの手柄にするような人もおり、そのような取締役を野放しにしていると組織を壊れてしまう。そして今まで社会貢献活動を行い、社員や取引先を大切にしていた企業が上場した途端、乱暴でまるで偽善者のような企業へと変貌していく。しかし誰もが知っている企業でも非上場を貫く会社もある。例えばサントリー、竹中工務店、アイリスオーヤマ、モンベルなど…。
そもそも上場することのメリットは証券取引場の厳しい審査を経て上場したことで、社会的信用が高まり多くの投資家から資金を集めることができ、その資金を設備投資や商品開発資金に充てることで、さらに利益を拡大することができる。また上場前から株主だと上場時に大きなキャピタルゲインを手にすることもできる。
逆にデメリットは多くの株主から目先の利益を追求することが求められるため、今まで醸成してきた企業文化や大切にしてきた社員や取引先との関係よりも利益を優先してしまうことになり、企業の自由度やアイデンティティまで失ってしまうことになる。しかも敵対的な買収や投資ファンドに目をつけられ買収される恐れすらある。
そのため長期的な安定した経営を重視している企業にとっては上場することが魅力的でない場合も多いようだ。
非上場会社であるアイリスオーヤマは企業として健全な成長を続けることにより社員を守り、社会貢献する企業を目指している。企業として社員とその企業を取り巻くステークホルダーを大切にする企業は、社会から広く愛され社会にとって必要な企業に成長するだろう。
経営者は決して安易に上場を考えてはいけない。
written by ジェイク