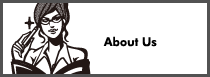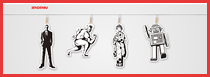濃霧注意報が発表された今週、朝方は福岡の中心部のビルが見えないほど霧が掛かっていたが、午後には霧はすっかり晴れ青空が広がった。翌日は雨の予報だったので、愛犬Q次郎を連れて西区にある小戸公園に散歩に出掛けた。この公園はヨットハーバーに隣接され、海を挟んで間近に能古島を見渡すことができるが、海にはまだ深い霧が掛かり能古島は全く見えない。
「能古島が見えんな。陸地の霧は晴れたばってん、海はまだ霧が掛かっとるんやな~」
そもそも霧は視界が1㎞未満で、100m以下の霧を濃霧と呼ぶそうだ。霧は極めて小さな水の粒で、霧吹きの水の粒よりもさらに小さな水の粒が空気中に浮かんでいる状態だ。空気には水蒸気という形で水が含まれており、気温によって空気中に含まれる水蒸気の量は変化する。暖かい空気にはたくさんの水蒸気が含まれているが、冷たい空気では水蒸気は少ない。気象条件により気温が下がると、余分な水蒸気は水の粒となり目に見えてくる。この現象は沸騰したヤカンの口から出た直ぐの湯気は高温で透明だが、ヤカンの口から少し上の方では、冷やされた水蒸気が水の粒となって目に見える現象と同じだ。自然の中で空気が冷やされる原因はいくつかあり、数種類の霧があるそうだ。
まず「移流霧」と呼ばれる霧は、冷たい海流に高気圧によって温められた湿った空気が流れ込み、海流で冷やされ水蒸気は水滴となり空気中に浮かぶもので、この霧は風向きによっては陸に入ることもある。次に「滑昇霧」は空気が沿岸の山に沿って上昇するときにできる霧で、高度が上がるほど気温は下がり山の斜面に沿って上昇した空気は冷やされ、余分な水蒸気は水滴となり空気中に浮かび霧になるそうだ。「滑昇霧」も「移流霧」もそれほど背の高い霧ではなく山を越えることはなく、沿岸で霧が出ていても内陸では晴れていることがあるという。さらに内陸では、「放射霧」と呼ばれる霧が発生する。日の出前は気温が最も低く空気中の余分な水蒸気は水滴となって霧が発生し、太陽が昇り気温が高くなると消えてしまう。「放射霧」は秋に発生しやすく、日中雨が降り夜になって晴れた時に発生しやすい。
今週、福岡で発生した霧は初夏のような天気で湿った空気が流れ込み、まだ冷たい海水に空気が冷やされ霧が発生したのだろう。今年の福岡のGWは例年より気温が高いようだ。それでは皆さん熱中症に気を付けて素敵なGWを! GWにQ次郎の伸びた毛をカットしてあげよう。GWでブログの更新は2週間お休み。ヤッタ~!!