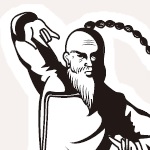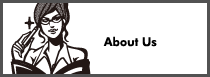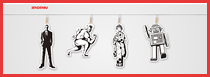つい先日、おせち料理を食べていたかと思うと、もう2月に入り明日は節分だ。2月は日数が少ないので、あっという間に3月になり春が訪れる。年初に掲げた目標に早く取り組まないと、年末の採点で高得点を狙えなくなってしまう。ヤバ…。
ところで先週末、長年お付き合いしている東京キー局で働く親しい先輩が来福したので、食事をすることに。彼は昭和の営業スタイルを今も貫く営業マンで、広告業界では名の知れた存在だ。彼にテレビや広告業界のことを尋ねると、彼の顔は曇った。
「今の時代、誰もテレビなんて見ないよ。広告も激減してるし…」
「そんなに業績は悪いんですか?」
高度経済成長期から、テレビは国民的メディアとして広く親しまれ、社会に絶大な影響力を与えてきた。ところがネットやスマートフォンの普及とともに、現在、「テレビ離れ」が進行している。実際のところ、「テレビ離れ」はどのくらい進んでいるのだろうか。
NHKが5年ごとに行っている「国民生活時間調査」2020年版では、平日の1日のうち、いずれかの時間帯にテレビを見る国民の割合は「79%」で、5年前の「85%」から6ポイント減少している。世代別で60代以上は同水準を維持しているのに対し、10代から40代は全て10ポイント以上落ち込んでいる。そして最も下落率の大きい世代は「16~19歳」のティーンエイジャーで、5年前の71%から47%と24ポイントも減少し、10~20代においてはほぼ半数がテレビを見ていないという。
「テレビ離れ」の原因はネットやスマートフォンの普及と、それに伴うネットコンテンツの拡大だ。多くの世代でスマートフォンを閲覧することが習慣になり、コンテンツやゲーム、それに漫画アプリなどが定着し「テレビ離れ」が加速している。そのため民放キー局5社の売上高はいずれも減少し、とくに広告割合の大きい「スポット広告」の収入が、各局とも前年度から10%以上も下落しているという。
また大手広告代理店の調査では2020年におけるテレビの広告費は、ここ10年間で初めて1.7兆円を下回った。一方、ネットの広告費は年々上昇傾向で、2019年にテレビ広告を超え、2020年は2.2兆円と最高値を記録した。
「一緒に暮らしている高齢の母は相変わらず一日中テレビを見ていますが、僕はテレビを見なくなりましたね~」
そう先輩に伝えると、
「お袋さん、テレビ見てくれてるんだ。有難いな~。テレビは今じゃ、年寄りのメディアになったんだよ」
栄枯盛衰というが、時代は大きなうねりを繰り返し変化していく。子供の頃、僕にいつもチャンネルを奪われていた妹はヒーローアニメや戦隊ものを仕方なく見ていた。